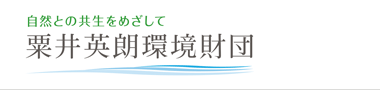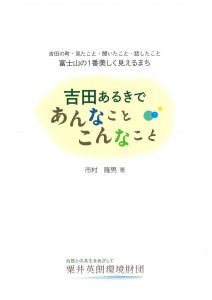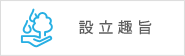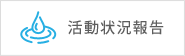粟井英朗環境財団|活動状況について
HOME > 活動状況について

クリーンフットパスを実施しました!
去る8月24日、「吉田の火祭りコース」と称したクリーンフットパスを北口本宮冨士浅間神社から御師町にかけて実施いたしました。
今回は案内を「富士山世界遺産ガイドマイスター」である桑原賢次氏に依頼し、8月26日、27日に開催される日本三奇祭であり国の重要無形民俗文化財にも指定されている「吉田の火祭り」に関連する内容を含め、コース上を解説をしていただきました。
神社内を十分に案内していただいた後、御師町に向かいます。火祭り当日には百本もの大松明が立てられる通りの脇には、既に松明が置かれており着々と準備が進んでいる様子を間近に見ることができました。
8月26日の夜に2基の御神輿が奉安される「御旅所」の会場になる上吉田コミュニティーセンターを折り返し、西念寺を経由し帰路につきました。
回収をしたゴミを分別し、可燃物20ℓ、不燃物少々となりました。
火祭りは山じまいのお祭りと言われているように、夏の終わりを感じられる気候を期待しておりましたが、当日は残暑厳しい陽気で、温暖化の影響をひしひしと感じる回となりました。
富士山自然観察会を実施しました!
粟井財団では、富士山の自然について学び、身近に親しむことでその環境を保全する心を育むこと目的とした「富士山自然観察会」を定期的に企画しています。
8月10日には講師に内山高先生を迎え、かねてより関心の高いテーマであった火山や溶岩に関する観察会を実施いたしました。
当日は12名の一般参加者、財団関係者、講師を合わせた18名にて、富士山の側火山の「雁ノ穴」「小臼」、梨ヶ原内の溶岩流を観察いたしました。
視察先1ヵ所目の「雁ノ穴」は、平成16年に改定された富士山ハザードマップに新たに加わった火口です。
北富士演習場内にあるため普段は足を踏み入れることは出来ませんが、立入日を確認し、県に許可申請し、恩賜林組合に入山鑑札を必要分発行していただいた上で当日を迎えました。
まずは 5世紀~7世紀頃の噴火によって出来た「溶岩トンネル」とトンネルの一部が崩れた「崩れ穴」を観察。冷気が漂う神秘的な場所でした。
続いて溶岩トンネルの北側にある、小高く盛り上がった場所へ。かつて雁ノ穴火口と思われていたこの場所は溶岩塚(ホルニト)で、実際は100mほどの南の一直線の溝が火口であることが2000年以降に行われた現地調査にて確認できたそうです。
溶岩塚の中央には大きな穴が開いているので、立ち入る場合は足元に注意が必要です。
雁ノ穴を後にして、2カ所目の「小臼」に向かいます。小臼は、忍野村立さかな公園の駐車場に隣接する約1万年前に噴火した古い側火山です。
今は木々に覆われてうっそうとしている火口は丸く、周囲に遊歩道があるので一周を徒歩で散策することが出来ます。また、小臼の周辺には、大臼、臼久保、膳棚の3つの側火山があり、いずれも約1万年前に噴火活動をしていたそうです。
3か所目の視察先は、梨ヶ原内の通称「見晴らし台」に向かい、そこから観察できる溶岩流について解説をしていただきました。
山中湖手前の小高く盛り上がった鷹丸尾溶岩が市街地まで延び、その上に広がるハリモミ純林までを観察することが出来ました。
今回の側火山や溶岩流の観察会を通じて、富士山の様々な様式による噴火の歴史を学ぶと同時に、迫力ある景観を目の当たりに出来た半日でした。
富士山自然観察会を実施しました!
去る7月28日、講師に富士山生物多様性研究室の渡邊通人氏を迎え、植物や昆虫に焦点を当てての富士山自然観察会を実施しました!
まずは富士山麓標高1,100mに位置する水資源保全のための整備森林にて、整備前と整備後の森林をそれぞれ歩き、植生の違いについて講師より解説をしていただきました。
また、植生調査結果によると、整備前森林には77種の植物が、整備後森林は106種の植物が観察され、その内整備をしたことによって68種を観察することができたとのことで、間伐や草刈りの整備によって草木層がいかに豊富になったかということを教えていただきました。
整備森林の観察後、梨ヶ原草原に向かいます。草原内では環境の違う2カ所を案内していただきました。
毎年4月に行われている「火入れ」によって草原環境が維持されている梨ヶ原草原。普段は演習場として使われているので、立入日を確認し、入山申請を行った上で観察会を企画しました。
全国的にも面積が激減している草原環境ですので、今回も沢山の貴重な草原性の植物や蝶を観察することが出来ました。
また植生調査によりますと、整備森林には187種の植物が、梨ヶ原草原には146種の植物が確認でき、その内、整備森林のみに確認できた種が116種、梨ヶ原のみに確認できた種が75種ということでした。
このように同じ富士山麓であっても手入れの仕方やその場所の環境条件によって大きく植生が異なり、植生が異なることによって昆虫や鳥などの動物の種類も変わることが分かりました。
身近にある自然を観察することで、自然に親しみ大切に思う方が増えることを期待し、今後も自然観察会を開催して参ります。
クリーンフットパスを実施しました!
去る7月6日、「富士癒しの森研究所」周辺を散策するフットパスを実施しました!
集合場所とした山中湖村役場に隣接する約40haの敷地内に「東京大学富士癒しの森研究所」が在ります。
様々な森の機能の中でも「癒し」の機能を研究対象にしており、7月14日(日)には6:00より「癒しの森の朝もや音楽会」が企画されています。
今回は今年度財団助成事業の対象でもある音楽会の紹介も兼ねて、研究所の周辺2㎞弱のコースを散策しました。
今年の2月からは、研究所林内の一部を平日9:00~16:00に一般開放しているそうです。詳しくは研究所のHP等よりご確認ください。
途中、山中湖漁業協同組合事務所に立ち寄り、室内の展示物見学をさせていただきました。年間を通じて様々な魚種を放流している他、子供たちを対象に地引網体験を行っているそうです。近年種類によっては漁獲高が減るなどの課題についても教えていただきました。
また漁業組合事務所のすぐ近くには、財団の寄付事業を活用し設置された電気自動車用急速充電器があり、丁度電気自動車が充電をしている様子を見ることが出来ました。
約1時間半かけて2㎞弱を散策し、拾ったゴミを分別。可燃物15ℓ、不燃物数個の結果となりました。
ゴミは大変に少なく、月に一度の村内一斉清掃や、常時ゴミを拾う雇用があることを聞き、美化意識の高い地域であることが分かりました。
参加者からは「ゴミが少なくて驚いた」「大通りからは分からなかった爽やかな森の中を気持ちよく歩けた」「山中湖にウナギを放流している話を聞き、以前父が台風の後山中湖畔でウナギが道路を泳いでいたという話を思い出した」などの感想をいただきました。
標高1000m前後に位置する山中湖村内でも当日は30度を超える気温を記録したそうです。湖の全面結氷もしなくなり、湖の魚の生態も温暖化の影響を受けているという話を聞き、避暑地であっても年々に暑さが増していることを実感した回となりました。
2023年度公募助成事業 成果発表会を実施しました!
6月15日と16日の2日間にわたり、2023年度公募助成事業 成果発表会を山梨県富士山科学研究所 ホールにて実施しました!
初日の15日は環境保全部門10団体、2日目の16日には地域振興部門19団体の発表と情報交流が行われました。
環境保全部門にて2023年度高評価団体に選出された「シオジ森の学校」様より活動報告を頂いた後、9団体の活動報告をそれぞれの展示ブース前にて行っていただきました。
活動報告の後は情報交流の場を設け、互いの活動について直接話をして交流する機会を設けました。
2日目の地域振興部門の会場では、2023年度顕彰事業の表彰式も併せて実施しました。
顕彰対象となった「富士河口湖町勝山スズ竹伝統工芸センター」の代表者より団体概要や活動状況などお話をいただき、会場内に展示ブースも設置していただいた上、助成団体との交流も図っていただきました。
また、地域振興部門の高評価団体5団体による発表の後、14団体の助成団体からも短い時間ではありましたが活動報告を口頭で行っていただきました。
なお今回選出された5つの高評価団体は以下のとおりです。
特例認定 特定非営利活動法人 富士の緑とフードサポート/富士吉田杓子山パノラマトレイルラン実行委員会/笹子追分人形保存会/助産院フジサンバ/女性シェアハウス 星の虹
計19団体の発表の後は、初日同様に情報交流時間をとり、各自自由にブースを回っていただきました。
情報交流後の閉会式では、出席いただいた選考委員の皆様よりお言葉を賜り会を締めくくりました。
今回で12回目となった公募助成事業。これからも環境保全や地域社会に貢献をする団体の皆様を応援してまいります。団体の皆様の活動の輪がますます広がっていくことを心よりご期待申し上げます。
『吉田あるきで あんなこと こんなこと』を増刷しました!
クリーンフットパスを実施しました!
去る6月1日、道の駅富士吉田周辺エリアを廻るクリーンフットパスを実施しました!
富士散策公園駐車場での開式後、鐘山の滝に向かいます。
ふじさんミュージアムを中心にして古民家カフェや紅葉回廊などが含まれる「富士の杜・巡礼の郷公園」は昨年の4月2日にリニューアルオープンし、その一画にある鐘山の滝もデッキが整備されたことで大きく様変わりしました。椅子も設置され、滝と緑をゆっくり楽しめるようになっています。
「富士の杜・巡礼の郷公園」の駐車場北側には、こちらも昨年8月に運用を開始したばかりの「山梨県営 ふじのしずく発電所」が建立されていました。家庭約17軒分の発電能力があるそうで、長期停電時の非常時にはコンセント盤のカギを市役所が開け、7口のコンセントが利用できるとの案内でした。
小倉山団地前を通り、道の駅富士吉田裏手を過ぎた場所には、ジビエ加工センターが建設中。近々オープンする予定とのことで、ジビエの処理加工だけでなく、販売や学習施設も兼ね備える充実した施設のようです。シカ肉の有効活用に期待が高まります。
道の駅富士吉田の南側、富士山方面には広大な散策路が整備されており、この日も沢山の人が散歩に訪れていました。
約2.5㎞、1時間半の行程で集合場所の富士散策公園駐車場に到着。
ゴミは想定していた量よりも少なく、可燃物40ℓ、不燃物20ℓでした。
2022年には富士吉田忍野スマートインターが開通し、ますます利便性の高まった今回のエリア。
人が多く行き交う場所ですが、ゴミは少なく、とても快適なフットパスとなりました。
朝霧草原の環境保全活動に参加しました!
富士山麓は、多くの草原環境が残っている地域として全国的にも有名です。
草原は火入れや草刈りなど人が手を加えることで維持され、放置されると樹林化し消滅します。草原は樹林に比べて地中に浸透する水分量が多いことから水源涵養機効果が高いと言われており、また、草原は樹林より多くの炭素を土中に蓄積させることからCO2抑制効果が高いとも言われています。このように有益な機能を発揮している場所として、草原の存在価値は高いと言えるでしょう。
山梨県内の草原と言えば「梨ヶ原草原」が有名ですが、お隣、静岡県富士宮市の「朝霧草原」は根原区財産区内にあり、根原区と朝霧高原活性化委員会によって、観察会や講習会、茅刈り体験など多種多様な活動が行われています。
当財団では朝霧草原での活動を応援するために年間を通じて参加をしております。
去る5月26日には「アズマネザサ抑制実験」が開催されました。
アズマネザサは繁殖力が強く、地下茎が横に広がり生息域を拡大することで、茅として資材活用されるススキの生育を脅かしています(写真下)。何とかアズマネザサの生育を抑制することはできないかと、4年前より試験区を設け実証実験が行われています。
具体的には「アズマネザサを草刈機で刈ることで生育抑制が出来るのでは」との仮説により、草を刈る時期と回数などを組み合わせ試験をしています。2024年度は5月と7月、11月の3回の草刈を行い、その効果を検証するとのことです。
(写真左下:5月26日に行われた草刈実施後の試験区 写真右下:昨年7月に行われた草刈実施後の試験区)
希少な草原環境を保全するため、これからも地域活動を応援してまいります。
グリーンカーテンを設置しました!
当財団では、事務所内に射し込む日差しを遮り、エアコンの稼働抑制による節電を目的として、毎年3か所の窓にグリーンカーテンを設置しています。
今年も5月下旬にネットを張り、2カ所にキュウリを植付けました。ゴーヤは6月上旬に植付け予定です。
キュウリやゴーヤは実を収穫することができますので、7月から9月にかけて事務所敷地内にて販売し、売上は苗代などの資材費に充てています(写真下)。昨年はキュウリ1株当たり約40本を収穫することが出来ました。ゴーヤは生育が旺盛で日光の遮断機能は高いのですが、近年実の収穫が少ないことが課題です。
劇的な温暖化により富士山麓標高900m程に位置する財団事務所でも、30度を超える日が年々増えてきていますが、室内のブラインドと屋外のグリーンカーテン設置により、エアコン稼働は今のところ数日で抑えられています。
今年も、これまでの栽培の反省点を活かしながらグリーンカーテンを育て、地球温暖化防止に貢献してまいります。