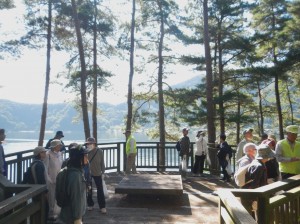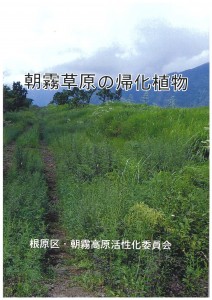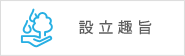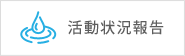粟井英朗環境財団|活動状況について
HOME > 活動状況について

整備森林におけるチョウ類調査結果について
粟井財団では、水資源の保全を目的として富士山麓標高1,100mに位置する森林にて草刈や除伐、間伐作業を行っております。
併せて、これらの作業が森林に生息する動植物の生態にどのような影響を及ぼしているかの調査をこれまで各種専門家に委託をしてまいりました。
2024年度、富士山生物多様性研究室に委託し2024年4月から10月にかけて実施されたチョウ類調査結果についてここに概要を報告いたします。
******************************
【調査方法】
・4月~10月にかけて月2回の調査実施(4月は1回)
・好天の日の9:00~16:00の時間帯に調査コースを1㎞/h程度の速度で歩きながら、コース両側5mの範囲に出現したチョウ類全種の種名、個体数、時刻などを調査表に記録
・現在林業作業をすすめている森林内では全長約800mのコースを設定
・2013年~2017年まで作業を行った森林内では約2,000mのコースを設定
・その他に梨ヶ原草原内など5つのコースを設定
【調査結果】
・現在作業をすすめている森林内には1年を通じて27種のチョウが確認された。この森林を特徴づける種として環境省絶滅危惧ⅠB類ヤマキチョウと山梨県準絶滅危惧オオチャバネセセリが挙げられる。オオチャバネセセリは森林内のミヤコザサ群落で発生したものと考えられる。その他の種ではヤマトスジグロシロチョウやヒメウラナミジャノメ、アサギマダラの個体密度が他のコースに比べ高かった。これはそれぞれの主食草である植物が生息しやすい、間伐や草刈を実施した環境が反映されたと言える。つまり、間伐や草刈といった作業によって植生環境の多様性が高まり、その結果としてそれらを利用するチョウ類の生息を促し、生態系の多様性を高めたと言える。
・2013年~2017年まで財団が作業を行った森林内には1年を通じて44種のチョウが確認された。この森林を特徴づける種として環境省絶滅危惧ⅠB類ヒメシロチョウとヤマキチョウが挙げられる。特にヒメシロチョウが高密度で確認されたことは特筆されるもので、春に発生した個体が梨ヶ原草原に戻って産卵することで、春の火入れによる越冬個体群の減少を補完しているのではないかと考えられる。
******************************
チョウ類は幼虫のほとんどが草食性であることから、多くの種類のチョウが生息する環境は、草原植物の多様性も高いと考えられます。このようにチョウ類は草原環境の生物多様性を測る上で重要な指標となっています。
これからも森林整備作業を進めることで高まる富士山麓の生物多様性に期待し、併せて観察会や調査結果についての学習会を開催することで生態系の保全啓発を図ってまいります。
エコプロダクツ展2024視察研修会を実施しました!
去る12月4日、東京ビックサイトにて開催されている「エコプロ2024」の視察研修会を実施しました。
当日は8:30に中型バスにて財団事務所を出発し、11:00~15:15までの現地自由行動、17:30に事務所到着の行程となりました。
産官学の各ブースは趣向を凝らした展示を披露し、小中学生の校外学習としても賑わっておりました。
頂いた参加者の感想は以下のとおりです。
・自然エネルギーに関する講演を受講した。商取引を行う上で環境配慮をしているかどうかは重要さを増していると思う。
・災害用のトイレのブースがとても参考になった。また自動車ではあらゆるパーツがリサイクルされていたり自然素材を使おうとしているところが凄いと感じた。
・土について知りたいと思い、土壌肥料学会のブースに行った。ミミズの糞で出来たイヤリングが印象的だった。
・会場に子供が多く、環境について学ぶ姿に嬉しく感じた。
・錆補強の取組みが金属を長く使う観点からも印象的だった。
・ピーファス対策について情報収集を行えた。
・SDGs達成のための企業努力をおおいに感じられた展示会だった。
・都市鉱山について学ぶことができた。
・コーヒーのリサイクルブースでの説明が印象的だった。
・ペットボトルの蓋のリサイクルブースが印象に残った。
などなど。
来年も是非研修会を企画したいと思っております。
木工体験教室を実施しました!
去る11月30日、富士吉田市青少年センター赤い屋根にて「木工体験教室」を実施いたしました。
地元産の木材とLEDランプを組み合わせたオリジナルキャンドル作りを参加者に体験していただくにあたり、富士北麓森林組合様と(有)ビー・クリエイト様にご指導とご協力をいただきました。
開会式の後には、木材にLEDランプを設置する穴を開けるデモストレーションを旋盤を使ってのご披露。
デモストレーションを終え、早速作業を開始。当日は老若男女42名の方にご参加いただきました。
オリジナルキャンドル作りの他に、カラマツの筆立、ヒノキの団扇にもお絵描きやデコレーションをし、約1時間の作業を終えてた後、各人オリジナル木工をお持帰りいただきました。
自然の木のぬくもりをご自宅でお楽しみいただければ幸いです。
クリーンフットパスを実施しました!
粟井財団では月に1度、清掃活動を行いながら地域の環境や文化歴史について学ぶ「クリーンフットパス」を開催しております。去る11月16日、今年最後の回となるクリーンフットパス「上吉田地区コース」を講師に天野安夫氏を迎え実施しました。
上吉田コミュニティーセンター駐車場にて開会式を行った後、早速活動をスタート。
今回は御師町周辺約4㎞を案内いただきました。解説をいただいた箇所とルートは以下のとおりです。
大国屋→筒屋→小佐野家→西念寺→吉祥寺→根神社→地蔵寺→塩谷宅→渡辺家宅→菊田家→善導寺→小御岳神社里宮→外川家→中雁丸表門→身禄堂
講師の天野氏には13ページにもわたる解説資料を準備いただき、廻った場所について詳細に分かるようにしてくださいました。また、多くの御師の家の入口には案内板が設置されているので、それぞれの特徴について深く理解をすることが出来ます。
約2時間をかけて地域を廻り、回収したゴミを分別した結果、可燃物60ℓ、不燃物30ℓとなりました。
最後に講師より「地域のことに関心を持たれる方は地域外から来た方が多い。是非、地元住民の方にももっと地域の歴史を知っていただき大切にしていただきたい」とのお言葉をいただき閉会。
世界文化遺産に登録された富士山の山麓周辺には、江戸時代に隆盛を極めた富士山登拝にまつわる場所が多く存在します。これからもフットパス活動等を通じて、地域の歴史文化を学ぶ機会を作るとともに、ゴミを回収することで富士山麓の環境美化に務めてまいります。
「みんなの食堂 赤い屋根」に富士吉田市産新米を提供しました!
粟井財団では地下水を育む田畑を保全することを目的に富士吉田市内で生産をしたお米を買い上げて取り扱いを行っております。
去る11月15日、2024年度新米を地元住民の方に味わっていたくことで地元農業の大切さや必要性を実感していただくため、富士吉田市内にて月に1度開催されている「みんなの食堂 赤い屋根」(主催:NPO法人 富士北麓まちづくりネットワーク)の参加者に新米を提供いたしました。
当日は配布する米の生産者である堀内治氏に来場いただき、富士吉田市内における米生産の現状や、食味における高冷地の優位性、提供品種「たきたて」についてなどをお話しくださりました。
参加者100名の方1人につき2㎏の新米を帰りにご提供。美味しさを実感していただき、地域農業への関心を深めてくださることを期待しております。
富士山美化活動を実施しました!
去る11月9日、富士吉田市青少年センターを集合場所として、その周辺約5㎞の清掃活動を実施しました。
今回のルートはゴミが多いことから、2016年より毎年実施しているコースとなります。
開会式を終え、早速活動を開始。
当日は天候に恵まれ、道からの紅葉を楽しみながら参加者同士の交流も図れたようでした。
回収したゴミを分別した結果、可燃物200ℓ、不燃物100ℓの結果となりました。
昨年は可燃物350ℓ、不燃物170ℓでしたので、今年は約1/2の量となりました。また5年前と比べると約1/5となり、ゴミの量は減少傾向にあります。
今までコース上にあった自販機が撤去されており、缶ゴミが少なくなったことや、財団関係者で今年2回清掃したこと、他の個人や団体もゴミを拾ってくださっているのでは、等々、要因は様々考えられますが、ゴミがゴミを呼び込まないよう、定期的に清掃を続けたいと考えております。
富士吉田市農業まつりに出店しました!
去る10月13日、秋晴れの中ふじさんミュージアムパーク内の芝生広場にて「富士吉田市農業まつり」が開催され、当財団もブース出店をいたしました。
これまで会場となっていた富士山アリーナが解体工事中のため、今回初めて芝生広場での開催となりました。
会場面積はこれまでと比べて格段に狭くなり出店ブースも減りましたが、財団で行った「農業&富士山クイズ」の参加者は144名と例年並みの人数でした。
クイズは6問で、富士吉田市の農業統計と富士山の登山者・来訪者数についてなどを設問としました。
144名の参加者の内、全問正解者は36名。正解者の方には木工品を、不正解の方には参加賞としてチョコレートをプレゼントいたしました。
関係者の皆様、終日大変にお疲れさまでした。
クリーンフットパスを実施しました!
去る10月12日、クリーンフットパス「奥河口湖さくらの里公園コース」を実施いたしました。
富士河口湖町内には主なものとして9カ所、町立の公園があるそうです。今回はその内の1つである奥河口湖さくらの里公園内とその周辺を散策いたしました。
当日は2011年より公園の草刈やトイレ清掃などを担っている長崎山さくらの里づくり協議会の方々と役場の公園担当者に出席いただき公園内を案内していただきました。
開会式の後さっそく公園内に向かうため山の坂道を登ります。
公園内には頂上広場と3つの展望デッキが整備されています。頂上広場からは辛うじて富士山の頂上が望め、それ以外からの場所では富士山を見ることが出来ないのが残念ではありましたが、3つの内最もデッキの大きい第1展望デッキではアカマツの隙間から河口湖を広く見晴らすことが出来ました。
3つの展望デッキを廻った後、木製のデッキ歩道の階段を下りて湖畔に向かいます。
展望デッキも木製歩道も部分的に木が朽ちていて、園内に入る場合は足元への注意が必要です。
湖畔の草地は協議会で年4回草刈を行っていることから、湖畔沿いを問題なく歩くことが出来ました。またここ10年内に植樹された桜が25本あるとのことで、春の時期は桜が楽しめそうです。
公園を後にして、長浜地区の中心街方面に向かいます。
足和田ホテル手前の古民家を改装し最近宿泊施設としてオープンした「THE LAKE 河口湖暮し」に立ち寄り、こちらを運営する小佐野代表に施設概要についてお話を伺いました。
施設は1棟貸の宿泊用途以外にウェディング会場やレストランとしても活用しているとのことです。当日は海外からのお客様が連泊中とのことで中の様子は伺うことは出来ませんでした。
集合場所の公園駐車場に戻り、ゴミを回収。今回は協議会の方で分別と処分をしていただきました。可燃と不燃を合わせて50ℓ程となりました。
閉会式では参加者の皆様より、感想や公園の利活用についての意見をいただきました。
・公園内のデッキの維持管理を続けていくことは大変なことだと感じられた。
・ミツバツツジが沢山植えられていた。湖畔の遊歩道の草刈を年に4回されているとこのことで大変なご苦労だと思う。
・河口湖町内に住んでいて公園の存在を知らなかった。親子参加型のイベントなど開催すれば認知が広がるのでは。
・せっかく管理している公園なのでもっとPRをすると良いと思った。
・外国の方が大勢サイクリングを楽しんでいたので駐輪しやすくすればSNSでも紹介してもらえるのでは。
・トイレがとても綺麗だった。
当日は天候に恵まれ穏やかなフットパスとなりました。
参加者の声にもあったように今後公園がより多く活用されることを期待いたします。
環境保全地視察研修会を実施しました!
去る9月29日、環境保全地視察研修会を実施し、静岡県富士宮市内の2カ所に赴きました。
午前中は富士教育訓練センターにて開催された「朝霧草原自然環境保全フォーラム(主催:富士宮市根原区)」に参加。朝霧草原の帰化植物とアズマネザサ抑制実証実験報告について2名の講師よりそれぞれ解説をしていただきました。
朝霧草原の帰化植物については、講師の佐野先生より48種の帰化植物を丁寧に解説していただきました。
またススキの生育を阻害するアズマネザサ抑制実証実験については、2020年より設定した試験区におけるアズマネザサの草刈結果について木村先生に解説をしただいた上、今後に向けた課題についてお話を伺いました。
午後は更に足を延ばし、「田貫湖ふれあい自然塾」にて「季節の自然さんぽプログラム」に参加いたしました。
敷地内を約1時間かけてインタープリターの方に案内いただきました。
自然に関する解説の他、途中で虫、リス、ムササビに関するクイズを出していただき大変に盛り上がりました。
最後は「秋」をテーマに参加者が俳句を作るという企画で締めくくりました。
流石の案内技術に参加者も感心しきりでした。
帰路の車内にて参加者よりいただいた主な感想は以下のとおりです。
・帰化植物の解説がとても分かりやすく、沢山の種類を覚えることができた。
・身近な雑草が帰化植物であることを知り驚いた。挿絵が丁寧に書かれており感心した。
・田貫湖に久しぶりに来たが施設が増えており変貌に驚いた。
・ふれあい自然塾のガイドが楽しく、様々に学ぶことも出来て有意義だった。
・自然解説と俳句が楽しく印象に残った。
普段意識をすることのない身近な自然にも、明治以降に海外から入ってきた外来植物が多いことや、アズマネザサのように年々勢力を拡大する在来植物があることを学びました。
午後の自然ガイドでは、まだまだ知らない自然の奥深さを楽しみながら認識することが出来、1日を通して学びの多い研修会となりました。
改めて、地域の身近な自然環境を観察して実態を学び、次世代に伝えて参ります。
クリーンフットパスを実施しました!
去る9月14日、クリーンフットパス「赤十字病院周辺コース」を実施しました!
今回のコースはこれまでも何回か清掃活動を行っており、ゴミのポイ捨てが多い場所として印象に残るエリアです。
今年も集合場所に富士北麓森林組合様の駐車場をお借りし、開会式の後、早速フットパスをスタート。
富士北麓森林組合施設は剣丸尾溶岩流上に建設されいます。今回も施設から程ない場所にある東海自然歩道を入り、道の途中にて勝俣理事より剣丸尾溶岩流についての説明を伺いました。約1000年前の噴火で流れ出た溶岩流上のアカマツ林は美しく、残暑厳しい日ではありましたが林内はとても涼やかで、癒される空間でした。
山梨赤十字病院を折り返した後、アカマツ林沿いを南に歩き、反時計回りに国道139号に合流します。
後半は国道139号沿いを歩き集合場所へと向かいます。
約2時間、2㎞程のコースを散策し、ゴミの分別の結果、可燃物120ℓ、不燃物30ℓとなりました。
今回初めての参加者からは「丁度良いコースだった。ゴミは思ったよりも少なく感じた」との感想をいただきました。またこのエリアを良く知る参加者からは「いつもよりゴミが少なかった。今日近隣でイベントがあるので事前清掃を行ったのでは」との感想をいただきました。
次回は奥河口湖のさくら公園周辺を散策いたします。
ご参加お待ちしております。

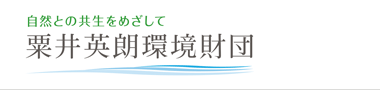







1-300x225.jpg)
-300x224.jpg)



-300x225.jpg)