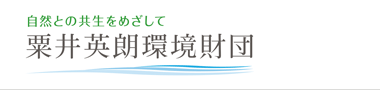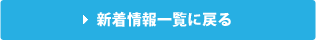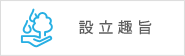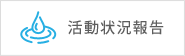粟井英朗環境財団|野鳥観察スキルアップ講座を実施しました! [ 新着情報 ]

野鳥観察スキルアップ講座を実施しました!
2025.5.9
去る5月6日、野鳥観察スキルアップ講座を、講師に山梨県富士山科学研究所 研究員 水村春香氏を迎え実施いたしました。
講座の前半は富士山科学研究所1階ホールにて講義を、後半は屋外の生態観察園での観察会の予定でしたが、開催当日はあいにくの雨でしたので、後半は室内にて鳴き声のレクチャーや質疑応答に代替いたしました。
前半の講義「鳴き声を知ろう、探そう!富士山麓の鳥」では①富士山の鳥類相とそれを取り巻く現状②鳥類相モニタリングについて③音響による研究について④鳴き声クイズ⑤まとめ の構成で進めていただきました。
富士山は多様性豊かな自然環境により鳥類相も豊かな地域です。しかし世界的には、人間の活動が主要因として「第6の大量絶滅時代」と言われ、日本では身近なスズメも絶滅危惧種になってしまうペースで減少しているそうです。また、シカの増加や外来種の増加も在来種の鳥類への影響が懸念されているとのことでした。
鳥類保全のためには現状把握のためのモニタリングが必要で、その種類と方法についても教えていただきました。
また、鳴き声には、主にオスが子育てをする季節に発する「さえずり」と、ふだんの会話となる「地鳴き」があり、それらが同時に、また複数の種類も同時に鳴く状況での聴き分けを調査現場で行っているそうです。
そこで今回、参加者の皆様も「鳴き声クイズ」に挑戦。同時に鳴いている5種類の鳴き声が何の種類か、そして「さえずり」か「地鳴き」かを考察しました。
最近はAIによる自動検出にも取り組まれていて、今後の業務効率化が期待されます。
前半の講義を終え、屋外での観察のため施設の外に向かいます。しかし当日の降雨により軒下からの観察のみとなりましたが、そこでも鳴き声がいっさい聞こえず、といった状況でした。
気を取り直し、再度室内にて、屋外で観察されたであろう種類の鳴き声を録音音声にてレクチャーをしていただきました。
カラ類は、シジュウカラ、ヒガラ、コガラ、ヤマガラなどおりますが、聴き分けるためには、まずシジュウカラを基本としてインプットし、それとの違いを聴き分けるとよいとのアドバイスをいただきました。
また、おすすめブックリストやWEBサイト、アプリも紹介もあり、事後学習のフォローもしていただきました。
参加者からの質疑応答の後、予定より早めに解散。
今回、屋外での観察が出来ませんでしたが、教えていただいたことを参考に身近な野鳥を観察することで、自然環境への関心をより深めていただくことを期待しております。